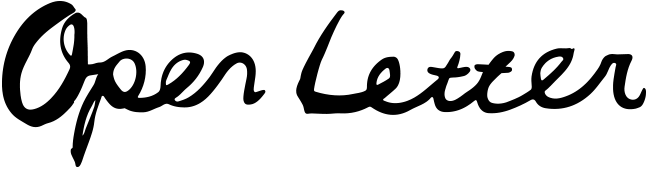芦川瑞季 インタビュー『散歩と制作 / 平面に集中する』
2020-02-01

リオープンしたOpen Letterの初回企画『気を散らすための日溜まり』の作家、芦川瑞季さん。
芦川さんはリトグラフを主な技法として、散策中に不意に出くわすさまざまな風景をモチーフに、現実と仮想を往還するようなイメージをモノクロームの版画作品として制作しています。
近年は、シェル美術賞2018入選、第19回グラフィック『1 WALL』ファイナリスト(第2位)、TOKAS-Emerging 2019 選出、さらには今年2月25日から予定されている三菱一号館美術館での個展など、活躍の場を着実にひろげています。
そんな芦川さんに、制作の過程や作品との向き合い方などを伺いました。
(2019.11.9、上北沢散策後にて/聞き手:山内・中庭、インタビュー構成:中庭)
ストーリーが
はじまりそうではじまらない
漫画への憧れ

ー制作に興味を持ちはじめたきっかけを教えてください。
芦川:
はじめは漫画を描くことが好きだったんです。中高生の頃、ギャグ漫画みたいなものを描いていました。
ーどういうギャグマンガだったんですか?
芦川:
『ちびまる子ちゃん』が好きで。実家の静岡はさくらももこの出身地で、家に彼女の漫画やエッセイが全部ありました。お母さんや親戚がさくらももこだったら買ってくれるんです。
作品の長さがある程度あって、ほのぼのしていておもしろい漫画に憧れがありました。
美大も、さくらももこは行ってなかったからどっちでもよかったんですけど、行きたい学校が他になくて、唯一受かった油絵科に行きました。そしたら全然なじめなくて。やっぱり、ちびまる子ちゃん好きだから、歴史の重さがわからなかったです(笑)。
どうしようかと思い、2年生から3年生に変わるとき、油絵学科から版画学科へ学科を変更しました。版画をやっている人たちって、もともと他のメディアを扱っていたり、留学生だったりで、外から入ってくる人に寛容なんです。
ーその頃も漫画は描いていたんででしょうか。
芦川:
途中までは頑張って描いてたんですけど、あまりうまくいきませんでした。
まるちゃんのように、ストーリーを完結させるのがすごく難しくて。
描きかけの漫画とか、ストーリーがはじまりそうではじまらないものとか、まるちゃんでもたまにギャグになっていない話とかあるじゃないですか。『コジコジ』とか、不思議な感じで終わっちゃったり。そういうのが好きでした。
もしかしたら、1枚の版画の画面でなら表現できるかもしれないと思ったのが、版画をはじめた大きなきっかけかもしれないです。
ー漫画はずっと描いていたんですか?
芦川:
そうですね。人に見せるためのものと、自分で描いてるだけのものと。中学や高校生の頃は、美術部の友達と小さい絵や漫画を交換していました。
ー何かの賞に作品を出したりもしたんですか?
芦川:
学部の1、2年生の時に、少女漫画誌に一度出して、全然だめでした。
やっぱり、まるちゃんがすごい好きだったから、さくらももこに影響を受けたようなものを描いていました。
漫画はいいですが難しかった…。コミティアやデザフェスにも出したんですが、難しかったですね。なにかこう、形だけやっている感じがして。3年生になってから版画科に入ったし、大学の方をちょっとは真面目にやろうと思って、一度漫画をやめて版画に集中することにしたんです。
版画って何だろうな…。イラストレーションでも絵画でもグラフィックでもなく、着地点が曖昧なメディアだから、自分で見つけられるものがあると思って。それで版画が結構面白くなってきて、人に見せたいなと思い、そのまま大学院に行き、結局博士まで。版画ばっかりやってます(笑)。
編集している自分が
どこかにいる状態を作る
ー版画の中でも、なぜリトグラフを選んだんですか?
芦川:
消極的な理由だったんですが、木版画や銅版画ではないなと。木版画や銅版画は削った線にインクが乗って、白黒が反転するので、わからなくなるんですよね。あと、それぞれ質感があって、木版画は刷ったら木目や水性のグラデーションが出たり、銅版画だと余白のところもグレーっぽくなったりと、どんな絵も少し味が出るんです。その味とか物質感みたいなのがうまく使えなくて。ちょっと障害になるのかもしれないと。
リトグラフは、石版の石やアルミのプレートに油性の鉛筆などで描いて、製版し、版画のプレス機に通すときれいに再現できる技法なんです。描いたものに対して忠実に出やすいけど、間接的な部分もある。そういう平面メディアに興味があります。グラフィックや絵画でもなく、丁度いい距離感に立てるのがリトグラフだと思って、今専攻しています。
他にもシルクスクリーンも迷ったんですが、描いた線をそのまま出すのがちょっと難しい。
インクを上から落とすのが物質っぽくて、プレスの機械を通してつぶして刷る方が、何か得られる感覚が違う気がしたんです。平面に集中したいと思ったから、潰して刷るほうにしました。

リトグラフの石版
ー写真でもなかったんですね。
芦川:
写真は距離感が難しいんです。撮った場所やモチーフ、被写体との関係性が近いというか。版画なら横にそれていくことができそうだなと。
ーリトグラフはどういう距離感になるんでしょう。
芦川:
全部の工程を自己完結できるけど、編集している自分がどこかにいる状態を作れるのが、版画だと思っています。個人で作品と向き合う時間や距離が得られるんです。絵画とまた別で、監督している自分がいるというのも、版画の強みだと思います。
もしかして違うかもしれませんが、例えば油絵だと、絵の具と対話したり、何か物質とずっと向き合っているような気がして。版画とは目的や見ている世界、受け取り方が違う感じがします。
ー版画を選んだ積極的な理由もありますか?
芦川:
版画だと、作品に対して無責任になることができる気がするところでしょうか。そもそも版画は、浮世絵などでもそうですけが、流動的なメディアなんです。浮世絵は日本独自の文化や美術だと言われてるのですが、確か浮世絵がはじまる前の江戸時代に、銅版画や西洋の宗教画が入って来て。
それから、北斎などの絵師たちが版画でどう表現するか流行ったんですよね。浮世絵って、色彩が綺麗だとか、平面的な中にすごい遠近感があることで、西洋の人に評価されているのですが、逆に日本人が、西洋の絵画を何とか理解しようとして、限られたメディアの中で試していったものだから、いろんな文化や絵師本人がいいと思ったものが、ふわふわ浮いたまま続いてると思っていて。
そういうコンテキストが版画にあるから、ただ見て、勝手に解釈して描くということが、版画では可能になると思うんです。
判断停止の態度を
作品に還元する

ーまわりには自身の出生や人生を作品に出す作家もいるけれど、自分はそういうの苦手で、という話がTOKASのインタビューであったと思います。それも作家と作品の距離感の話だと思って聞いていました。
芦川:
版画を専攻し始めた時は、作品の背景をわかりやすく構築することについて考えてました。
最初は何も作れていなかったし、技巧も全然わからない状態だったので自信がなく、先生に「こういう作家は参考になるから観に行きなさい」と言われるがまま観に行きました。すると、絵は参考になるのですが、作家自身の背景を伝えることは個人の問題だから、あまり参考にならなくて。
見ている人に伝わりやすいことは重要だと思います。作品の制作背景がわかりやすい方が広く人に知ってもらえて活動しやすいかもしれないですし、そういう作品は確かに観たらよく覚えています。でも自分に当てはめるのが難しかったんです。
実家の静岡は、恵まれすぎてるんです。みんなすごいのんびりしていて、山があって、海の幸もあって、水も綺麗で、何もない。
だから私の場合、作品と自分の関係性を別のベクトルで捉え直す必要がありました。
ー自分の人生を作品の強度にしていくことはやらないことにして、ではどういう方向にいこうとしたんですか?
芦川:
版画を始めたばかりの大学3年生の頃、何も思いつかないから、とりあえず1カ月間くらい家の近くをずっと散歩をしている時があったんです。すると見えてなかった何かが見えてくると思ったことがあって。例えば、学校にある百葉箱が空間から白く浮かんで見えたことがありました。
百葉箱は温度計などが置かれていて、子供たちが天気の勉強をするためにあったけれど、もう使われないらしいんです。ただ置かれているだけですけど、何か特別なものにも見える気がするし、すごく要らないものにも見える気がして。
そういうものと、漫画や描きかけのままで残っていたイメージみたいなものを重ねて描くようになったのが、いまのスタイルの作品制作のきっかけだったと思います。

『パーソナルスペース03』2016年制作 lithgraph on paper
現象学に「エポケー(判断停止)」という概念がありますが、これは目の前で見ているものを「留保」の姿勢で、後から自分の中で時間かけて解釈することだと私は受け取っています。
絵の具は動かせるから、ペインティングだと画面が統一されていくイメージがあるんです。そうではなく、イメージとイメージがぶつかったまま描き起こして固定され、そのまま刷り起こされてしまう状態が、何かを留保したり、見たままの印象を描けたまま提出するような、下書きのまま清書されるような状態を作りたいんです。
版画をとおして、誰かに何かをわかりやすく伝えたいというよりかは、見たものをそのまま保留にしておく姿勢を可能にしたり、作品に還元することができたらいいと思うんですよね。最近はそんなことを考えています。
断片を編集し、とどめた版から
見えてくるもの

ー画面の構成はPhotoshopで組むと聞きましたが、どれくらい決めこんで配置するのでしょう?
芦川:
結構荒いです。消しきれてないカットがたくさん残っているし、写真作品として緻密な感じではなく、ブツ切りです。本当は紙切って貼り合わせるようなコラージュが一番いいかもしれません。コストかかからないからPhotoshopで配置していますが、結局ピンと来なくて、版に描いている途中で変えたりとか。上から別の絵を入れてしまうこともあります。
ー漫画的なカットを挿入するのはどういうタイミングですか?写真を撮った時点なのか、写真を組み立ていく流れの中でなのか。
芦川:
後者のほうですが、行ったり来たりしながら考えます。元々描きかけの漫画や、落書きやメモイメージはたくさんあって。
それをそのまま何かに加えるのは難しく、描きかけの漫画と写真を両方見て考えたり、組み合わせたり、どちらかを変えたり、描き変えたり、同時進行ですかね。

ー描きためていた漫画を使うとのことですが、写真をみてから思いついて描くということもありますか?
芦川:
それもあります。なぜなら場所と関わりがある展示が多いからなんです。TOKASの展示だと1年前から打ち合わせをしていて、この展示でどういうことができたらいいか、などの話をしていく中で、会場周辺の風景を撮ってみようとなりました。
展示の場のこととか何も考えないでつくる作品もあって、そういうものは写真と関係なかったりします。
ーその二つは芦川さんの中でどう違うんですか?
芦川:
写真を見て思いついたものを描くと、普段書き溜めていたものの中に出てこないものが描けたりしますね。
TOKASでの展示のあとに、その時のことが運動神経のように残っていて。パーソナルなイメージに入って来たりもするから、何かフォルダが増えた感覚はあるかな。両方行ったり来たりしているのが一番いいんだと思います。
ーそれは留保的なものでしょうか。留保の時間に、風景と自分が逆転するような、TOKASの時の話で言えば、圏内と圏外の逆転が起こるようなこともあるのですか?
芦川:
判断停止は作品を取り巻く全体に漂っているものであって、具体的な時間というものは意識していません。ですが、平面上のやりとりで主観的な判断から思いもよらない組み合わせが起こり、見えてこなかったものが見えてくることはあります。
ー見たものを留保の時間の中でとどめて、それが作品になっていっているわけですよね。風景と漫画の編集は、留保の時間の中で行われている、ということですか?
芦川:
そうですね。例えば散歩に出かけてそのまま気になったりしたものを写真で撮ったり、音を録音しても、ピンと来ないんです。結局いろんなメディアを疑ってしまうところがあって。見た断片から立ち上がってくるものを探しているんですが、それ自体を信じているわけではないんです。だから版で編集までやってしまうんだと思います。
2次元と3次元の間の
矛盾点をみつける
ーTOKASのインタビューで、「2次元と3次元の間に興味がある」とおっしゃっていましたね。
芦川:
態度だけだとやっぱり作品は作れなくて。何かを留保する態度を画面の中に残しておくために、2次元的なイメージと3次元的なイメージを混ぜています。
私が3次元の人間だから、扱える次元が2次元と3次元くらい。4次元とか5次元だとどうしたらいいかわからない(笑)。
『フラットランド』という本があるんですが、2次元の世界に住んでる人が3次元の世界の人に遭遇する話なんです。
フラットランドは平面の世界で、住んでるのは四角形とか三角形とか丸とかの図形。角が多いと階級が高く、丸が一番偉くて。
四角が主人公なんですけど、それの前に球体が現れるんです。球体は3次元と2次元の平面空間を行ったり来たりできるから、間の中で小さくなったり大きくなったり、消えたり現れたりができるんですよね。四角からしたらこの人は神様なのかな?と(笑)。
制作するときに、そういった『フラットランド』のイメージがなんとなくあるんです。
1個下の次元、2次元を意識して作ることで、どうしても重なりあわなかったり、矛盾してしまうところがわかるのかもしれないと思って。
散歩と制作
完全に私物ではない風景
ー芦川さんの作品には、家や緑が多いですね。
芦川:
本当にただ見ていて気になっているものを撮っているから、自分の好みとかフェチが入っているかもしれないのですが、歩いていて浮かび上がって見えてくるものは、人の生活の跡とか、他者の好みとか、思いもよらないところからの気配みたいなものなんです。オフィス街でもそういうものがあれば見てみたいし、扱ってみたいのですが、街がきれいに整備されすぎてて、気付かなかったり、見えて来ないのかもしれない。
緑が多いのは、もともと人の家の庭を撮っていたので。庭をずっと撮っていると、葉っぱの切り方とか、選んでる植物の種類とか、吊るされたオーナメントなどが見えて、自分だけの庭として作っているのか、通りすがりで隙間から見ている人のために作っているのか、気になるところがあります。そういうところから出発して、人に手入れされた緑が好きなんです。
ー庭って少し公共的というか、半分自分のものだけど、半分外に向けられていますよね。通りすがりの人に向けて、何かオブジェをおもしろく置いていたりとか。完全に私物じゃないような。
芦川:
完全に私物じゃない。でも撮っていると怪しまれたりとか。どっちなんだろうと(笑)。
例えば働いていると、求められるのは合理的なことだと思うんです、人も環境も全部。でも見えているものが100%合理的にならないで止まっていたり、ぶつかり合っている状態があって気になるんです。
人の感情や環境が、合理的なものに相殺されているイメージがある。そんなことを言葉で考えながら撮っている訳じゃないんですが、無意識的にそういうものに引き寄せられているのは、相殺される何かが見える気がするんですよね。

2019.11.9、上北沢散策風景
ー制作する上で、散歩は必須なのですか?
芦川:
必須にはしていないです。必須にしてしまうと、自分の立ち位置や作品との関係性が変わってしまうので。
例えば百葉箱のように、引き寄せられるように出会ったものが、逆に探しにいくものになってしまうと、関係性が変わってしまうなと。受動的だったものが能動的になってしまうんです。出会うために行動してしまうと、自分の世界を作っていってしまう。それが強まりすぎると、見たい風景と違ってしまうと思って。素材を探しにいくような、消費しているような感覚とは違うんです。
あと作品を作る時、時間の差を意識していて、過去に散歩したときの画像を見て作品を考えたりします。過去に残した記録と、今歩いていること、その時間差で作品を作るんです。
ー現在の制作スタイルに、影響を与えているものはありますか?
芦川:
ちょうどよい距離感でものを見ている人を探していたんですが、版画の分野ではいなくて、それ以外の分野で探し始めて出会ったのが、ベンヤミンや赤瀬川原平、今和次郎などです。
ベンヤミンは版画や映像やっている人だったらみんな読んでいるんですけど、“アウラ”とかより、ものの見方が気になったんです。
ベンヤミンの『パサージュ論』は最近読んでいる最中なのですが、影響を受けています。散歩しながらものを見ていると、現実と主観的なものが一緒になっていく感じが共感できます。
他にも『一方通行路』という彼のエッセイもおもしろいです。架空の街を歩きながら考えたこと、例えば、落し物、窓、思い出した批評、思いついた言葉など、一章ずつ展開されていて、そういう唐突な構成が参考になるなと。
ー哲学からも影響を受けているんですね。
芦川:
最近ようやくそういうの読むようになりました。ふいに目に入ってきたものを解釈して描くから、どうしてそれを描いているのか自覚したいんです。何も自覚しないままでも作品を作り続けることはできる。ですが同じ結果だとしても、制作のプロセスを続けながら目が冷めた状態になりたいというか。こういう本は自覚するのに参考になります。
それと、赤瀬川原平さんや今和次郎もすごく面白いです。今さんは民俗学と考古学を組み合わせたような「考現学」というのを提唱していて、当時の都市や風俗を記録していった人で。柳田國男に師事していて、一緒に活動していた時期もあったのですが、途中から一人で活動するようになりました。
服とか風景とか民家とか、記録的なものが多いかな。『日本の民家』という本もすごい。関東大震災の後、家がたくさん潰れてしまったときに、木材で仮に建てたバラック小屋の表面に、高級な家を描くみたいな活動もしていました。
赤瀬川さんは、見えてくるもの、気になるものを純粋に取り込んでいて、オブジェクトが優先されているんです。“トマソン”などは、いろんな人が報告したり記録したりしているだけだけど、誰が発見してもいい、というところがいい。
赤瀬川さんの作品は、形がどんどん消えていって、最後は文章や行動だけになってしまいますよね。物質が消えてものの見方だけが残っていくというか。
ー芦川さん自身も、物質的なこだわりよりも、“留保”や、ものの見方そのものを表現したいのでしょうか。
芦川:
そうですね。私の場合は完全に物質から離れることはまだできないのですが、作品をつくる動機になっていると思います。
(2020.02.01公開、02.07更新)